そんな指示じゃできません!中国企業の叫び
オフショア開発時代の「開発コーディネータ」(9):そんな指示じゃできません!中国企業の叫び
前回は中国オフショア開発に、元来向いている仕事と向いていない仕事があることを紹介し、それぞれの特徴を説明した。今回は、中国企業の信頼を勝ち取るために必要なオフショア開発コーディネータの条件を紹介するほか、昨今各種メディアで話題になっている中国における反日活動の緊急レポートをお知らせする。
2005年05月25日 12時00分 更新
今回は、中国企業の信頼を勝ち取るために必要なオフショア開発コーディネータの条件を考察します。
中国オフショア開発のあるべき姿を知っている
オフショア開発コーディネータは、自分がかかわるすべてのプロジェクトにおいて、あるべき理想的な姿を頭に思い描けなければいけません。多くの日本企業では、プロジェクトマネージャの間でオフショア開発の経験則が十分に共有されていないため、オフショア開発コーディネータの担う役割が大切になるからです。
第4回記事では日本企業が中国に嫌われる理由の1つとして、「木を見て森を見ず」的な発注形態があることを述べました。本連載では、このような発注形態に代表される従来型のアプローチを日本型開発アプローチと称して、日本側の態度を改善するよう強く求めています。オフショア開発において日本型開発アプローチはさまざまな弊害をもたらしますが、それらは以下のような中国企業の声に象徴されます。
「われわれは何を開発すればよいのか、仕様を説明されてもさっぱり分からない」
「日本企業の担当者はシステムの全体像を知らないうえに、業務知識も乏しい」
中国側の不満をより深く理解するために、「絶対に完成しないジグソーパズルの法則」を使って、あるべき姿を知っていることの大切さを説明します。
絶対に完成しないジグソーパズルの法則
あなたの目の前に、十分に大きなジグソーパズルが置かれています。このジグソーパズルに私がある細工を施すと、あなたはそのジグソーパズルを絶対に完成できなくなります。「ある細工」とは、いったいどんなことでしょうか。念のために前置きすると、パズルの一部を「隠すこと」でも「変形させる」ことでもありません。
正解は、あなたに「ジグソーパズルの完成図を見せない」ことです。
……。
「そんなバカな!」
「いくらなんでも、それはルール違反だ!!」
そう感じたあなたの感覚は正常です。しかし私たちは、これを悪質なジョークだと笑い飛ばせません。なぜなら、「絶対に完成しないジグソーパズルの法則」とまったく同じ現象がオフショア開発で頻繁に起きていることを、うすうす自覚しているからです。
システムの規模が大きくなると、全体を適切なサブシステムに分割して、さらにその一部の開発をオフショアのベンダに委託します。前出のジグソーパズルに例えると、ある領域を取り出して「その領域だけを組み立てるように」と指示するようなものです。
ところが、日本企業に痛い目に遭わされた中国側の意見はこうです。日本企業は、発注時にジグソーパズルの全体の完成図を見せてくれません。しかも、発注対象のサブシステムの完成図(仕様書)ですら「不完全」な状態がほとんどだと!
こうした「あるべき姿」の欠如は、仕様書の問題だけではなく、開発アプローチの認識違いをも引き起こします。
オフショア開発でトラブルが発生したとき、日本企業は自らの問題を棚に上げて一方的に中国側を非難しがちですが、事前にジグソーパズルの完成図を提示していたかどうかを自問すべきでしょう。そもそも、「社内の誰も完成図を知らない」といった状態かもしれません。これは笑い話では済まされません。オフショア開発で事前に提示すべき「パズルの完成図」のうち、特に日本企業が見落としがちな項目を列挙します。
プロジェクト全体像
- システム化の背景や理由、方針、目的
- 中国発注部分とシステム全体との関係
- ステークホルダーや関連部署のかかわり
日本側のやり方
- 開発プロセス、各種ルールや基準、使用する管理帳票、管理単位
- 各工程のINPUT/OUTPUTの定義
日本と中国ではトイレ掃除後の「あるべき姿」が違う
品質やサービスレベルを議論するうえで、「あるべき姿」の意識を統一することは、今後ますます重要になってきます。筆者が主宰する中国オフショア開発実践セミナーでは、より実践的な数値目標による品質計画手法を学びますが、その前提として品質やサービスレベルの「あるべき姿」が、両国の共通ビジョンとして周知されていることを見逃してはいけません。理想の姿が共有されていないところでは、どんなに厳格な定量指標を置いたとしても、品質向上にはほとんど役立たないでしょう。
ひと昔前、口の悪い人は中国製品を手にして「安かろう、悪かろう」といいました。しかし、多くの日本人が感じる「悪かろう」という感覚は、実際のところ、品質に対する両国民の価値観の違いにすぎないことが少なくありません。このことを証明するために、日本人が中国人にトイレ掃除を頼む場面を例に取って説明します。
日本人はよく「中国のトイレは汚い」といいます。最近では、北京や上海など大都市のトイレはずいぶんきれいになりましたが、それでも日本のトイレと比べると歴然とした差があります。
日本と中国の品質に対する価値観の違いを示すために、頭の中で1つの実験をしてみましょう。
上海のオフィスビルの中から、日本を訪れたことのない複数の中国人を無作為に抽出します。そして、日中文化の比較実験と称して、選ばれた人々にトイレをできるだけきれいに掃除してもらうようにお願いします。
その結果、トイレはどうなるでしょうか。「日本並み」にきれいに掃除されると思いますか?
「日本並みのキレイさ」を言葉で表現するのは難しいことですが、結果は読者の皆さんが予想されたとおりになるでしょう。中国都市部の平均的なトイレしか見たことのない人間は、いくら「できる限りきれいに掃除せよ」と依頼されても、絶対に「日本並みのキレイさ」にはならないはずです。
それは「日本人は清潔」で「中国人は不潔」という批判とはまったく異なります。要するに、日本と中国では、トイレ掃除をした後の「あるべき姿」が違うのです。日本のトイレを見たことのない中国人にとっては、ベストを尽くして掃除しても、日本人になかなか満足してもらえません。一方的に「品質が悪い」と非難される側には、ぬぐい切れない不公平感が残ります。
以上のことは、中国オフショア開発の品質問題にも通じるものがあります。お手本を示さないままでトイレ掃除を依頼する実験は、前出の「絶対に完成しないジグソーパズルの法則」とまさに同じ構造です。
ここで1つ疑問が生じます。日本の状況をまったく知らない中国人に、日本人が満足するレベルでトイレ掃除をしてもらうには、いったいどうすればいいでしょうか。
回答例
まず、日本の平均的なトイレを5~6カ所見学させるとよいでしょう。写真やビデオではなく、実際に現場で確認すると効果的です。可能であれば、日本人と一緒にトイレ掃除する経験を持つとよいでしょう。採算を度外視すれば、日本に2~3カ月の間、研修で滞在するという選択もありえます。
トイレ掃除に限れば、作業の手順を細かく定義して、作業ごとの「あるべき姿」を体感させれば、日本に長期滞在する必要はないと考えます。トイレ掃除の達人が何度も手本を示して、日本が要求する「完ぺきなやり方」でトイレ掃除を体験させてあげることを意識してください。
過日、筆者が発行するオフショア開発メールマガジンの読者から、次のような意見をちょうだいしました。
-------Original Message--------
Subject:北京の家、昔はきれいだと思っていたのですが
私は北京から日本に移り住んで10年が経ちました。
先日、北京に帰ったとき、昔はきれいだと思った実家がどう見ても汚く感じます。
頑張っても適応できなかったので、結局はホテルに泊まってしまいました。
この感覚は、中国オフショア開発の品質でも同じかもしれません。
-----Original Message Ends-----
北京出身の読者からの指摘のとおり、明確な基準がない限り品質やサービスレベルは相対的な価値観にすぎません。オフショア開発で発生する大半のトラブルの原因が、この点に集約されます。
「部屋をさっと掃く」
「動くことを一通り確認する」
われわれが頻繁に使う言葉が、人によってどれだけ差が生まれるのかを再認識しましょう。
緊急レポート:「中国全土に広まった反日運動、いまのところ日本企業のリスク対策は万全」
本連載で政治経済の話題に深く立ち入るつもりはありませんが、最近の反日運動がオフショア開発に与える影響には興味があります。大半の読者の方は、社内の限られた情報しか入手できないため、先の見えにくい中国情勢に不安を隠し切れないことでしょう。
中国全土に広まった反日運動が中国オフショア開発の現場事情にどのように影響しているのかを調査するため、オフショア開発専門メールマガジンの読者2600名に緊急アンケートを実施しました。
5月の大型連休までは、TVや新聞などのマスコミでは連日のように中国に駐在する日本人が登場して、「会社から外出禁止の通達があった」といった声が報道されていました。その後、中国政府が本腰を入れて反日デモの取り締まりを強化したこともあり、いまではすっかり沈静化した感があります。
アンケート結果を見ると、「対策済み」と「特に影響はない」を合わせると過半数を超えています。あらかじめ、テロや反日デモを予測した現地駐在員の安全マニュアルが規定されているのであれば、「対策済み」や「慎重に見守りたい」といった回答になるのかもしれません。また、悪影響はないという意味で「特に影響はない」と回答された方も多いことでしょう。
「中国で起きている反日運動を冷静に判断していただきたい」こう語るのは、上海市にテストのアウトソーシング会社を持つ倉田克徳氏です。倉田氏は「日本での報道は過熱気味ですが、節度ある行動を取っている限り、現地では身の危険は感じませんでした」と振り返ります。
一連の反日運動によって、多くの日本企業では、中国出張自粛の措置が一時的に取られましたが、中国に駐在する日本人社員を召還させるなどの「重大な」影響は、いまのところありません。2001年アメリカ同時多発テロ事件以降、日本企業のリスク対策は飛躍的に高まったように感じられます。いま一度、あなたの会社のリスク対策マニュアルを確認することをお勧めします。
中国全土で盛り上がった反日運動は、嵐のように過ぎ去ってしまいました。前出のように短期的な影響は小さかったものの、今後まったく不安がないわけではありません。報道によると、反日デモの主役の一部は中国の大学生でした。その結果、中国の大学生の間で「なんとなく日本企業を敬遠する」といった空気が流れるようだと、日本企業がこうむる長期的な損出は計り知れません。
中国オフショア開発に携わる技術者として、私たちは今回の反日運動をどのようにとらえればよいでしょうか。
まず、オフショア開発に積極的な中国企業には、反日感情を持つ社員はまず存在しないことを認識します。筆者を含め、多くの中国ビジネス専門家は、反日運動がオフショア開発業務に与える影響は小さいと予測しています。一連の反日運動に対しては、「過剰反応しない」を合言葉に、これまでと変わらぬ活動を続けていくべきだと考えています。
特に分散拠点で実際に開発に当たる技術者に対しては、日ごろから意識して日中両国の非公式な会話の量を増やし、共通の会話の土俵(コミュニケーション基盤)を固めることを強く推奨します。結局のところ、両国の技術者同士がどれだけ「何げないおしゃべり」に花を咲かせることができるかで、プロジェクト成否が決まってくるのですから。
profile
幸地 司(こうち つかさ)
アイコーチ有限会社 代表取締役
沖縄生まれ。九州大学大学院修了。株式会社リコーで画像技術の研究開発に従事、中国系ベンチャー企業のコンサルティング部門マネージャ職を経て、2003年にアイコーチ有限会社を設立。日本唯一の中国オフショア開発専門コンサルタントとして、ベンダや顧客企業の戦略策定段階から中国プロジェクトに参画。技術力に裏付けられた実践指導もさることながら、言葉や文化の違いを吸収してプロジェクト全体を最適化する調整手腕にも定評あり。日刊メールマガジン「中国ビジネス入門 ~失敗しない対中交渉~」や社長ブログの執筆を手がける傍ら、首都圏を中心にセミナー活動をこなす。
 | 本作品采用 知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 |



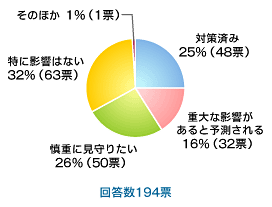


 浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号